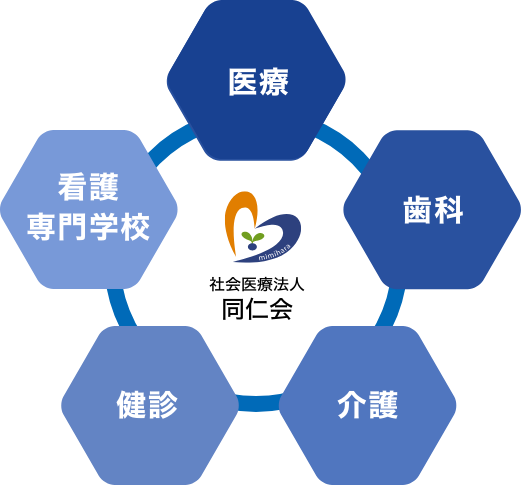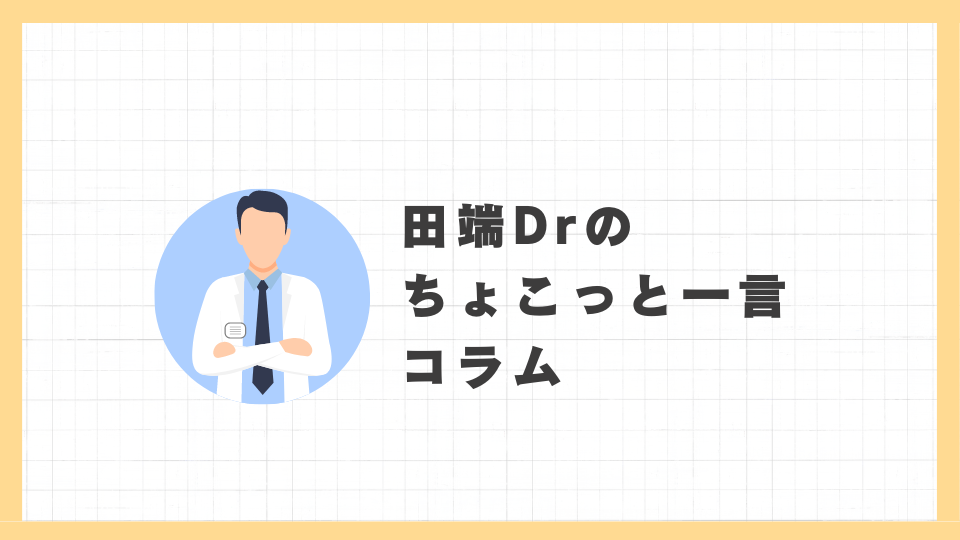わが国で「チーム医療」と言う言葉が使われ始めたのは、ちょうど私が医師になった頃ですから、30数年ほど前のことです。最初の頃の「チーム医療」は、医師が中心となって医療を行い、その他の職種は医師と連携してそれを補助すると言うものでした。現在のチーム医療の考え方は異なります。患者さんやご家族もチームの一員です。そして医療のみならず介護分野の職員まで、対等平等の関係でお互いの専門分野を活かして連携・協力し合い、患者さんとご家族の抱える問題を解決してゆきます。チームリーダーが医師である必要はなく、解決すべき問題によって適切な職種がリーダーとして振舞えばよいのです。
良好なチーム医療を阻む要因の一つに、医師の権威勾配があります。権威勾配があると、医師の出した方針に対して、他の職種が対等平等の立場で意見を言いにくくなるわけです。全ての医師がそうと言うわけでは決してありませんが、医師は一般的にプライドが高く、自分に対する批判に反発しやすいように思います(私もその一人だと思っています)。また、日本ではまだまだ「医師は全てのことを知っておくべき」、「全てのことは医師の判断に委ねなければ」という風潮があり、自立した専門家としての責任のある意見をあまり出さない医療職・介護職の方も見受けられます。これは患者さんやご家族も同様で、事務や看護師に情報を提供せず医師にのみ集中させたり、医師の指示だけに従う方もまだまだ多かったりする状況です。医療がチームで行われているのだということ、そしてその方が良質な医療を提供できるのだということが、当たり前の文化にならなくてはなりません。
チーム医療を良好にするコミュニケーションツールの一つに、SBAR(エスバー)と言うものがあります。Situation(状況)、Background(背景)、Assessment(評価)、Recommendation(提案)の順番で相手に自分の考えを伝えるもので、英語の頭文字を取っています。この「提案」の部分が大切です。「自分はこうしたほうが良いと思います」とチームの仲間に言うことは、自らの専門家としての知識と技量が問われることだからです。提案のない状況報告だけでも、チームで情報の共有ができるので良いのですが、きちんと自分の意見を言ってくれるチームメンバーがいると心強いです。その意見が優れていると、「ああ、この人はプロだなあ」と実感します。
私はこれまで、この「プロだなあ」と思える人たちに囲まれて成長してきました。自らの専門性にかけて、患者さんのためにどんどん意見を言ってくれた他職種のおかげで、助けられたことが何度もあります。耳原鳳クリニックでも、今ともに働く仲間たちは、チームメンバーとしてとても心強い面々です。「プロの姿」を見ると、自分ももっと良い医師になろうとモチベーションが高くなります。私は幸せな環境にいるのだと思います。これからも医療職・介護職同士で切磋琢磨して、良いチーム医療を提供してゆきたいと思います。