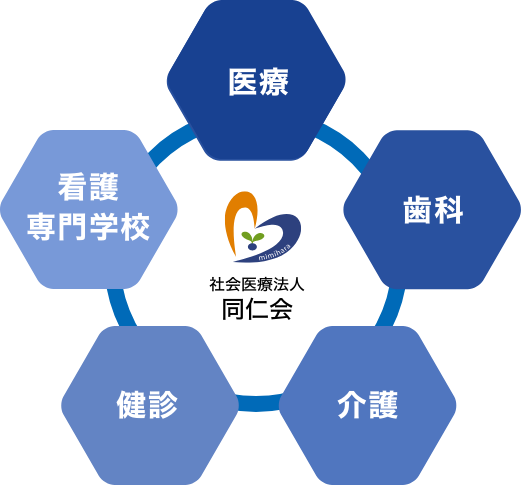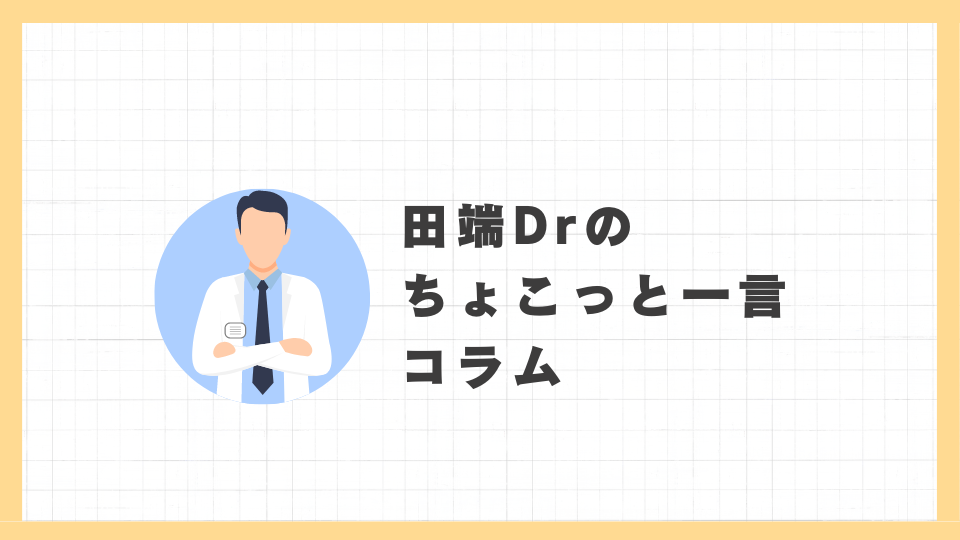前回は「患者さんの呼び込み」についてお話ししました。今回は医療面接と身体診察について、私が行っている手法をお話ししたいと思います。
医療面接は、以前には「問診」と呼ばれていました。問診だと「診断を付けるために、医師が患者さんに問いかける」ものになります。病気だけに注目するのではなく、「精神面や社会面をも含めた問題に対して、医師と患者さんが対話をする」と言う意味で、今は医療面接と呼ばれています。では実際に、診察室の中では「対話」が行われているのでしょうか?「先生はパソコンの画面ばかり見て、こちらを見てくれない」と言うことが、患者さんからよく聞かれる昨今です。
「対話」するには最低限、医師は体を患者さんの側に向け、目と目を合わせなくてはなりません。その上で「聞き取り」ではなく「言葉のキャッチボール」を行うのです。患者さんが紹介状を持って受診するような大病院の外来ならいざ知らず、当院の様なクリニックではとてもそのような時間をかけることは困難です。私はそのために、全ての予約患者さんのカルテを「予習」しています。前回の診察の結果から読み取れる今後の流れを把握し、患者さんに行った検査の結果を事前にカルテに記載し、結果に対する方針も考えておきます。方針決定が自分の力量だけでは難しければ、教科書やガイドラインを紐解いたり、他の医師に相談したりして、どのような対応をするのが適切か、事前に準備をしておくのです。患者さんが診察室に入ってきてから検査結果を見て「どうするのが適切だろうか」と考えていると当然時間がかかりますし、それらをカルテに記載するのにも時間がかかります。私は予習をしておくことにより、少しでも浮いた時間を患者さんに体を向け、視線を合わせ、対話する時間に充てています。私には毎週150名程度の患者さんの予約がありますから、全ての事前準備を行うことはなかなか大変な課題です。誰にでもお勧めできる手法ではないと思いますが、私には必要なことです。
最近は身体診察しない医師もいるようですが、論外です。患者さんに触れる行為は大きな安心感を与えます。ですが、患者さんに触れる前には必ず「失礼します」と声をかけます。脈をとる時も、結膜を見るときも、聴診器を当てる際にも、それぞれ「失礼します」と言います。だって患者さんにすれば、他人から勝手に声もかけられずに触られるなんて。本当に失礼でしょう?医師の方から「失礼します」と声をかけることは、患者さんと対等の位置に立つ準備なようなものです。
また、「得られた所見を必ず言葉にして患者さんに伝える」という手法も行っています。「結膜には…貧血はないし黄疸はありませんね。首のリンパ節は…腫れていないし甲状腺も大丈夫ですね。心臓の音は…雑音はないですし、肺の音は…とてもきれいですね」と一つ一つ所見をお伝えするのです。患者さんにとって診察行為と言うのはブラックボックスであり、医師が何を見ているのか、診察所見はどうなのか、気になるのではないでしょうか。患者さんからご感想を聞いたことはないのですが、身体所見を口頭でお伝えしながら診察することは、安心感を与えていると信じて、ずっと行っています。
同じ検査、同じ治療を行ったとしても、自分が診療した患者さんの方が良くなっているような医師になりたい。頂きは高く険しいですが、他の医師とも切磋琢磨して努力してゆきたいと思います。